はじめに
このウェブサイトSTUDIO Mのビジョンである、”マーケターとミュージシャンに自由を”について、株式会社メンバーズ執行役員である原裕さんと今後数回に渡ってディスカッションをしていきます。原さんは、アメリカンエキスプレスカード日本法人から株式会社メンバーズへと、マーケティング街道を歩んでこられたマーケティングの先輩であり、音楽について語り合える友人でもあります。二人の対話をお楽しみください。
日本のAI化の現実
松原: 原さんが最近の動向で着目されていることは何ですか?
原: やはりAI化の波(特に生成AI)は外せないでしょうね。パートナー企業様と話ていても、いよいよ、AIトランスフォーメーションが始まりつつあるなと感じます。単に社内のAI化による効率化を推進するだけでなく、AI化によって効率化される領域で働いているホワイトカラー人材のリスキリングも同時に行うことも含めてトランスフォーメーションを考えると言う企業もあります。本質的にはAIを活用した新たなビジネスモデルが生み出されていく時代に突入したのだと思ってます。
松原: そこまで行くと単なる効率化では無くて、企業のコスト構造が大きく変わりますね。一方で、日本企業にはAI抵抗勢力もまだまだ多いのではないですか。
原: そうですね。情報漏洩リスク、コンプライアンスなど、やらないための理由を列挙するのは簡単なんですよね。私は1996年からネットを主体としたマーケティング業務を生業にしてきたのですが、当初はネットを導入しない理由のオンパレードだったので、当時の状況とよくにているかもしれません。
松原: それでは、ますます日本企業の国際競争力が懸念されますね。私は企業活動の約770%は、データ化そしてDX化が可能だと考えていて、その究極の形がAI化だと思っています。一方で残りの30%は企業独自のアイデアや手法を活かす部分だと思います。AI化の流れは決して逆らえるものではないので、今日本企業がやるべきは、AI化に逆らう事ではなくてAI化できない30%の領域でいかに独自性を出して国際競争力をつけるかだと思うんですが、今の日本企業のマインドはどこにあるでしょうかね。
原: 例えば、マーケティングの領域のAI活用においてもWEB上にある口コミ情報や社内に蓄積されているVOC、売り上げ情報などをAIが収集・分析して、その情報を生成AIで誰でもが取り出せ、それに基づくインサイトを提案するようなサービスが可能なところまでは来ています。ただ、クライアント企業によっては、そのインサイト提案に基づいた商品企画提案までをAIに聞きたがる場合もあります。従来はその情報収集、分析に時間やスキルをようしていたので、その業務の専門性を持つ代理店などが担当していたケースが多いという背景もあります。
松原: その企画提案こそが、残りの30%に当たるマーケティングの面白いところなんですけどね。このケースでは、マーケター自らが、”それはAIに任さずに自分でやるよ”と言えることも重要ですね。
原: マーケターとしての仕事の本来の喜びを体感する事は大切ですね。Howの部分はAIに任せれば良いんですよ。
今、Whyが問われる
松原: 原さんと出会った20年近く前に、Simon Sinek氏の”whyから始めよう”というTED動画を原さんから教えたもらったのを思い出します。今、一周回って再びwhyが問われる時代になってますね。
原: まさにそうだと思います。ソニー、ホンダの様な終戦後に立ち上がった日本企業は明確なWhyを持っていたし、Appleは紆余曲折はあったもののSteve Jobsの whyを受け継いで発展しています。その後、インターネットの発展によって膨大なHowが進化しました。今起きているAI化はそれらをひっくるめてもう一度見直す機会でもありますね。
松原: 経営者の重要な役割ですね。一方で視点を企業から個人に変えると、自分の経験上、企業のwhyと社員個人のwhyが必ずしもピッタリ同じでなくても良いし、むしろその方が幸せを感じることが多かったように思います。企業のwhyと個人のwhyは、音楽で言うと、ハーモニーの様なものではないかと思います。つまり、全く、同じ音を出す必要はないく、ハモる音を出していればそれで良い。
原: そうそう。企業には時々フリーキーな音を出す奴が一人くらいいても良くて、それが引っ掛かりになって発展していくこともあるんですよね。企業独特の不協和音こそがその企業の特徴になるんだと思います。ベースになる和音はみなさん一緒なので。
松原: 経営者のwhyが和音で言うルート音(ドミソのド)になっていてその響きが強いほどその上に乗る音の許容範囲が広くなるんでしょうね。
余白の大切さ
原: 今起きていることやこれから起きることを色々考えると、AIは創造性を育む環境を作るもの、と位置づけるのが良いように思います。
松原 なるほどAIに余白を作ってもらうのだと。
原: 我々は検索機能の無い時代に育ちました。その時代にはアナログの面白さがありました。自分で出かけて好きなものを見つける喜びとも言えます。例えば、レコード屋を回ったり、古本屋を回ったり。今の若年層のアナログ回帰もその価値の再発見ではないかと思うんですね。企業のコンプライアンス、ガバナンスで余白が減っている結果、若い世代がそういうものを求めているのだと思います。
松原: 確かに、昔は、”面白いものは上司に隠れて作れ”と教わりました。その時代にも、コンプライアンスやガバナンスはあったけど、それを上手くバランスさせる知恵があったのだと思います。このまま大企業のガバナンス過剰が進むと面白い人やアイデアが企業から逃げて行くリスクを感じます。
原: メンバーズの初期の頃には、他社がやらない領域にいち早く取り組めたのが楽しかったですね。メンバーズの社風がそうでした。今はメンバーズも大きくなってなかなかそうはいかない部分もあります。でも、DXがコモディティ化した今、脱炭素に取り組むメンバーズの様なDX支援会社はクライアントからも面白がられるんですよね。企業自身、特に担当は目の前の業務や実績作りに身も心も(笑)捧げがちなので、少し先のことや未来のことに一緒に目を向けれる機会を提案しています。
余白を楽しめる人材
松原: せっかくAIが余白を作ってくれても、その余白を面白がる人材がいないと意味がありませんね。その人材を育てるにはどうしたら良いでしょうか?
原: やはり、リベラルアーツ、インサイト、体験価値(CX)といったキーワードになってくるように思います。リベラルアーツの重要性は、日本の偏差値教育では見落とされがちだと思うんですよね。でも大学からでは遅くて、私の娘が卒業した学校はカナダのブリティッシュ・コロンビア州の高校卒業資格も取れるのですが、そのカリキュラムの違いや学びのやり方には大変な驚きとともに刺激を受けました。授業はアクティブラーニング型で考え、_創造することに力点がおかれ、哲学の授業などもしっかりと組み込まれていました。また、高尾山に登り頂上で詩を読むとかもユニークでした。これらは体験を通じて物事を考える能力を培うことに役立っているのだと思います。答えを考えることも重要ですが、問いを考えることの重要性を学べたと思います。そして、それはマーケティングにおいてもCXがより重要になってきています。CXをリアルに感じてものを考える、自分の人生を充実させる、そういう生き方が大切なんじゃないですかね。
松原: 確かに、遊びの部分って大切ですよね。特に企業のwhyを設定する経営者の方には、遊び方を大切にしてもらいたいですね。ゴルフも良いんですが、もっと人生を豊かにする。ような遊び、例えば、Fuji Rockに出向いて聴衆に紛れて音楽を楽しむとか、自分のアトリエを持って絵を描くとか。ソニーの盛田昭夫さんは、若い人たちと当時流行っていたディスコに行ったり、スノボなどの流行りのスポーツをいち早くやったりと時代に触れるような遊び方をされてましたね。そういう経営者の設定するWhyは、社員にとことんサウンドすると思うんですよね。
原: 遊びに関して興味深い話があります。デンマークのデザイン大学の先生方とデザインについて議論した事があるのですが、デンマークにはデザインの4Pと言うコンセプトあり、それは、Planet, People, Play そしてProfitです。デザインの要素の中に遊びのPlayがしっかりと入っているんですね。そういうコンセプトに基づいて制度や街並みが設計されているので、国全体がとても美しく機能しているんですね。
日本が見直すべき自分達の力
松原: なるほど、デンマークから学ぶことは多そうです。一方で日本が古来から持っている国の文化としての強みは確実にあると思います。どの強みを活かせば日本は再び国際競争力を高められるでしょうか?
原: それは、自然と共存する力でしょう。それを生かしてサスティナブルな国になることです。今の日本は、東京と田舎がデバイドされている。デンマークでは、地方が風力発電を都会に売るというような都会と地方を結ぶ循環あるんです。そしてコペンハーゲンの人たちはカントリーサイドで遊ぶことをとても大切にしています。
松原: なるほど、自然との共生力は、都会に住んでいるととかく忘れがちですが、確かに東京から新幹線に乗れば、あっという間に日本は自然に恵まれた国だと実感させられますね。
おわりに
今回は、AIトランスフォーメーションの動向をきっかけに、企業のWhyの重要性、余白の重要性と楽しみ方、そして、日本の今後の活路にまで話が及びました。このシリーズ、暫くこんな感じで緩く続けて行こうと思います。次回もお楽しみに。
原裕(はらゆたか)
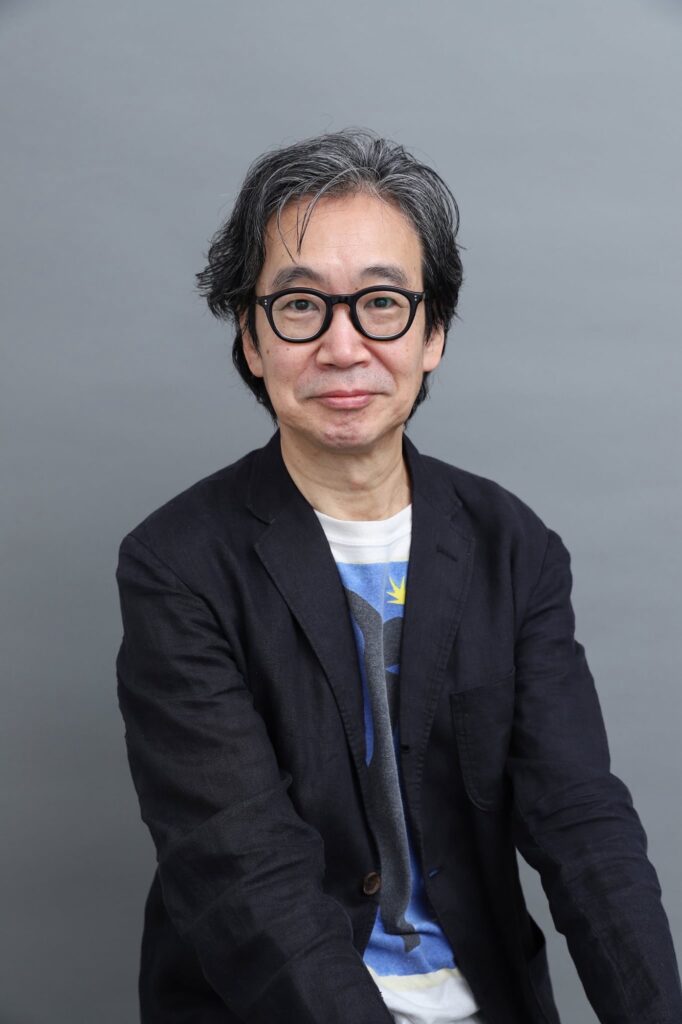
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル Inc.加盟店営業・マーケティング、キーアカウントマネージャー、Thompson Dialog 取締役ジェネラルマネージャーを経て、1999年より株式会社メンバーズにて大手企業のデジタル・マーケティング支援を行う。2023年よりメンバーズ 脱炭素DXカンパニーに所属し、企業の脱炭素推進支援を行う。著書として「フェイスブック・インパクト」「エンゲージメント・マーケティング」「SDGsが生み出す未来のビジネス」「脱炭素DX」など


